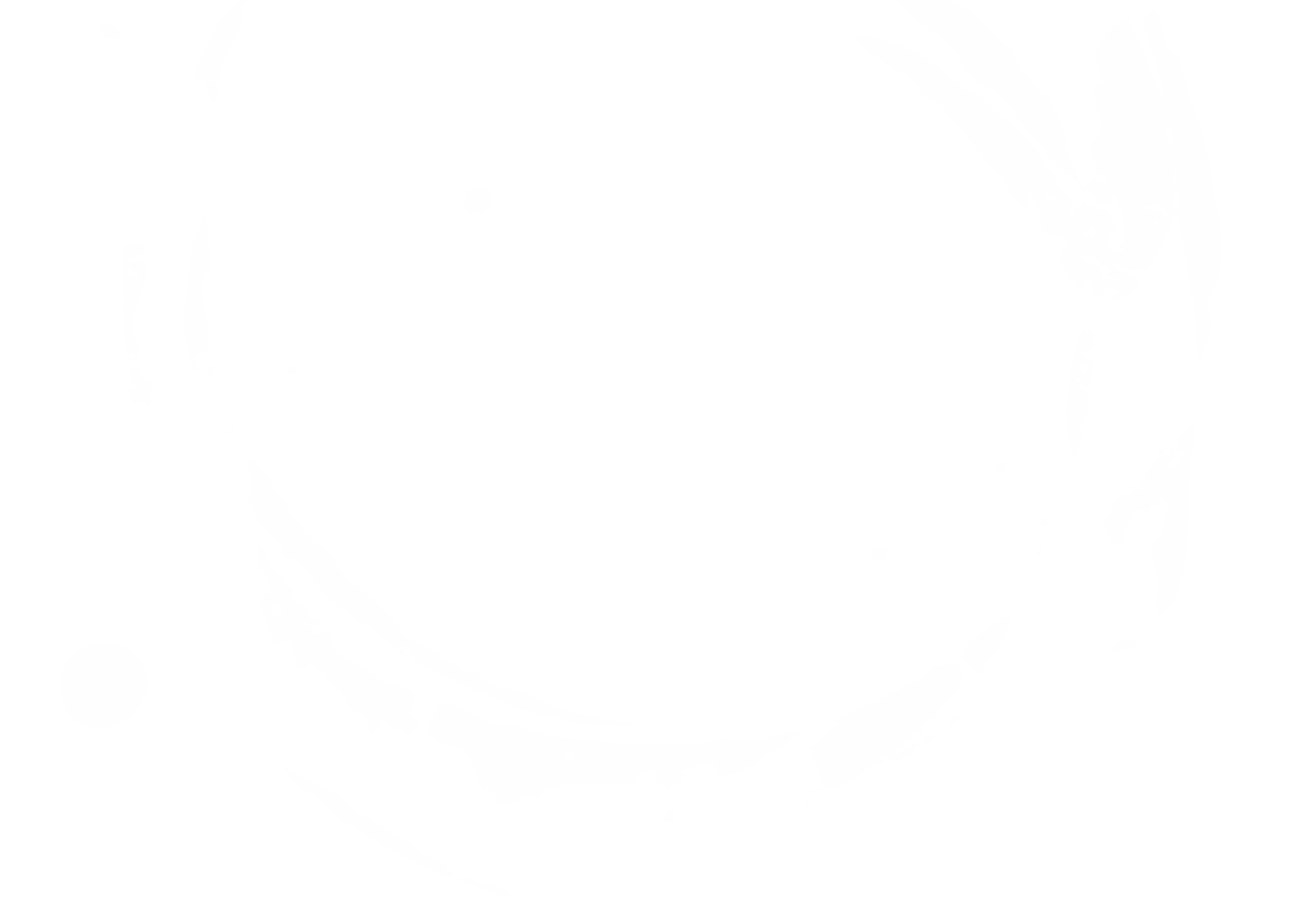ニュース 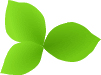 News
News
2022年
- 2022/12/05
-
M1の丸岡直弥さんが、「修士論文研究計画論第二」(中間発表)で、ポスター賞を受賞しました。
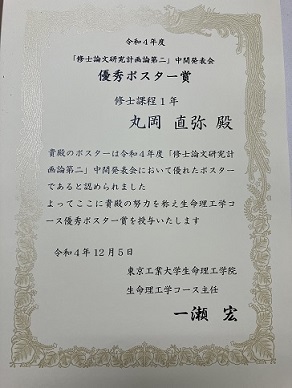
- 2022/10/18
- 本郷教授が共著の論文が、Scientific Reportsに掲載されました。アルギン酸コアをアガロースゲルで包埋した、1細胞ゲノム解析用の新規なマイクロビーズの開発に関する報告です。 実際にシロアリ腸内細菌叢などで用いた結果、多様な培養不能細菌種の高完成度のゲノム配列取得に成功しました。セルソーターのような高額な装置や特殊なマイクロデバイスが不要で、安価に1細胞ゲノミクスが実施できるのが特徴です。 理化学研究所の青木弘良研究員と雪真弘研究員を中心とした研究で、理研と東工大の共同研究です。(プレスリリース)
- 2022/09/20
〜5/26 -
米国ノースカロライナ州のアパラチア山脈で、琉球大学の徳田岳 教授とともにキゴキブリのサンプリングを行いました。


- 2022/09/15
- 本郷研OBの金城幸宏 博士の論文が、Microbiology Spectrumに掲載されました。 ゴキブリの細胞内共生細菌Blattabacteriumの比較ゲノム解析で代謝系を網羅的に解明するとともに、宿主であるゴキブリの代謝系と照合することで、栄養相補性の程度を検証しました。 その結果、アブラムシのような植物篩管食者とその細胞内共生細菌との関係とは異なり、明確なアミノ酸・ビタミン類合成の相補性はほとんど見られませんでした。 これは、宿主ゴキブリが雑食性であり、細胞内共生細菌の栄養面での貢献の仕方が異なるためと推定されます。OIST、東工大、理研の共同研究です。
- 2022/08/24
- 本郷教授が、「あのトップランナーが語る!微生物生態マラソンセミナー」で、「めくるめくシロアリ腸内複雑共生系 〜虫屋の目で見る微生物多様性〜」と題するオンライン講演を行いました。
- 2022/05/10
- 本郷教授が共著の論文が、FEMS Microbiology Lettersにオンラインで掲載されました。 シロアリ腸内細菌単離培養株で大豆を発酵させ、家畜飼料に利用するという研究で、タイ・カセサート大学のPinsurang Deevong 講師のチームが主導しました。
- 2022/02/19
- 本郷教授が、JT生命誌研究館主催で「シロアリはなぜ木だけを食べて生きられるのか」と題する一般向けのオンライン講演を行いました。
2021年
- 2021/12/07
- 猪飼桂 研究員の論文が、Molecular Ecologyにオンラインで掲載されました。 シロアリ腸内には複数種の木質分解性原生生物が共生しています。その種多様性を、「種」を「交雑可能な個体群」ではなく「同一のニッチを持つ個体群」として定義する「エコタイプ仮説」に基づいて、 コンピューターシミュレーションで推定しました。その結果、従来形態学的に10種類程度に分類されていたヤマトシロアリ腸内オキシモナス原生生物類が、約30もの種で構成されている可能性を見出しました。
- 2021/11/28
-
D1の高橋一樹さんが、日本共生生物学会第5回大会で、優秀若手発表賞を受賞しました。
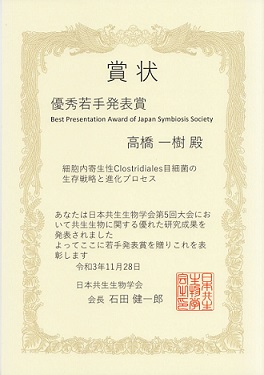
- 2021/08/28
- 本郷教授が、「大隅基礎科学創成財団」主催の市民講座「地球の多様性を支える仕組み」で、「シロアリはなぜ木だけを食べて生きられるのか?」と題するオンライン講演を行いました。